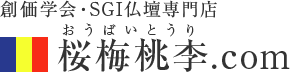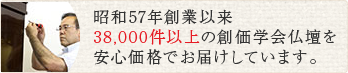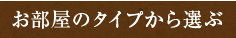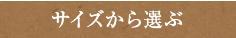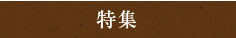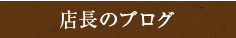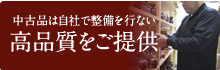大地震、大津波が発生した二〇一一年(平成二十三年)当時、元藤裕司は、学会にあって、大槌、釜石、大船渡、陸前高田など被害の激しかった地域の県長であった。
その日、彼は内陸部で仕事をしていた。釜石の自宅には、目の不自由な義母、妻、娘、乳飲み子の孫がいる。携帯電話もつながらず、家族や同志の安否が心配でならなかった。
まず自宅へ向かった。交通は規制され、身動きがとれなかった。翌朝、ようやく、わが家にたどり着いた。家の数メートル前まで津波が押し寄せたが、自宅も、家族も無事であった。御本尊に、ひたすら感謝した。
しかし、安堵に浸る間もなく、総県婦人部長である妻の福代と共に、会員の安否確認に回るため、家を出た。
街は一変していた。一面、瓦礫に埋まり、廃墟と化し、市街地に向かう道もなくなっていた。でも、なんとしても同志に会わなければならない。裏山の階段を上り、山中を歩いた。藪が生い茂る獣道を進んだ。前日から降った雪に足を取られながら、倒木や崩れた岩を越え、急斜面を下りると、今度は瓦礫が行く手を阻んだ。それを踏み越え、二時間余りを費やして市の対策本部に着いた。
そこで、各避難所の収容者の名簿を見て、学会員の名前を確認し、避難所に向かった。瓦礫だらけの道なき道を必死に歩き、この日、五カ所の避難所を訪ねた。何人もの学会員と会うことができた。
着の身着のままで避難所にたどり着き、一夜を過ごした人たちは、憔悴しきっていた。
元藤は、過酷すぎる現実に言葉を失った。
「よかった! よかった……」と、ただ手を握り、共に涙することしかできなかった。それでも、皆、喜んでくれた。同志の目に、次第に光が蘇った。
ともかく会うことから、思いが伝わり、心は結ばれる。行動に勝る雄弁はない。
被災者でありながら人びとの面倒をみて、忙しく立ち働く学会員もいた。信仰の力を、学会魂の輝きを見た思いがした。(聖教新聞より転載)
「現場第一、実際に人に会う、自分の目で確かめる。そこからすべてが始まる。思いを伝え、心が結ばれる!」